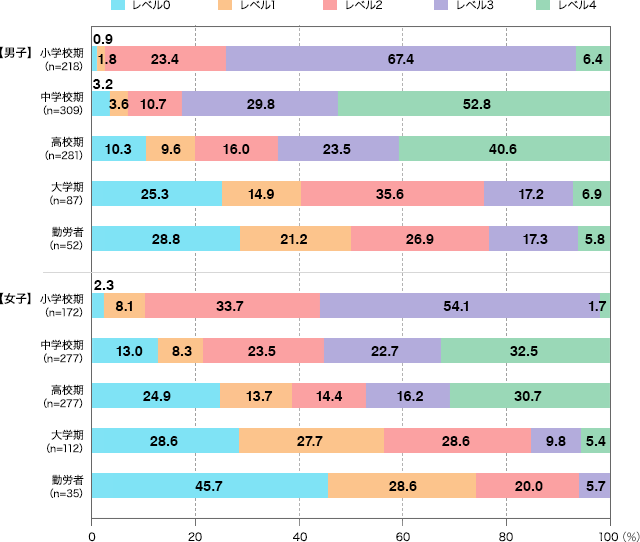あの、心の底からわき上がる感動から4年たった。
ドイツで開催された、2011FIFA女子ワールドカップ(以下、W杯)。あまりにも劇的だった決勝戦。勝利を決めた後の表彰台で喜びを爆発させる日本サッカー女子代表・なでしこジャパンの姿は、今も鮮やかな記憶として残っている。
当時、東日本大震災で傷ついた多くの日本人に、どれだけ元気と勇気を与えたか計り知れない。スポーツのもつ価値や本当の意味を、あらためて気づかされた人も多いのではないだろうか。
今年、なでしこジャパンは6月にカナダで開催される女子W杯で新たな高みを目指す。どういった結果になるだろうか。今から楽しみである。
しかし、世界一に輝いた日本の女子サッカー、実は長い間ひとつの大きな問題を抱えている。
『日本の女子サッカーの課題、それは中学生年代の育成だ』
昔からサッカー関係者や指導者が集まると、口を揃えて出てくる言葉だ。中学生年代の何が問題なのだろうか、W杯優勝後に変化はないのだろうか、どういった改善策があるのか―。
今回から全4回にわたって、女子サッカーにおける中学生年代をテーマに、スポーツやサッカーに携わる研究者や指導者のインタビューを中心に掲載していく。第1回は笹川スポーツ財団 スポーツ政策研究所 武長理栄研究員に話を伺った。
-
 武長 理栄 Rie Takenaga
2003年山梨大学大学院教育学研究科修了。2005年より(株)ルネサンス、スポーツ・エンジェルLLCで幼児の基本的動作に着目した運動遊びプログラムの開発や実践を行う。2011年10月より現職。
武長 理栄 Rie Takenaga
2003年山梨大学大学院教育学研究科修了。2005年より(株)ルネサンス、スポーツ・エンジェルLLCで幼児の基本的動作に着目した運動遊びプログラムの開発や実践を行う。2011年10月より現職。
女子中高生にみる「スポーツをする、しない」の極端な二極化
―まず、女子スポーツ全体の運動実施状況について教えてください。
武長10代男女の学校期別の運動実施状況をみると、『レベル0』という生徒がいます。学校体育以外の放課後・休日などで「1年間全く運動をしなかった」と回答した者を指していますが、女子をみると、中学校期で13%、高校期になると24.9%にのぼります。スポーツをしない女子生徒の割合が男子を大きく上回る。私の考えでは、特に女子において思春期の段階で、スポーツをする生徒としない生徒に分かれていくのではないかと思います。原因はさまざまあると思われますが、活発な生徒がいる一方で、まったく運動・スポーツをしない生徒もいるという、運動・スポーツ実施の二極化が起きています。(図1参照)
【図1】運動・スポーツ実施レベル(性別×学校期別)
資料:笹川スポーツ財団「10代のスポーツライフに関する調査」2013
小学1年生から高校3年生までのスポーツライフ・データからわかる問題点
―女子中高生のスポーツ実施人口の二極化という問題は、中学生年代の女子サッカーが抱える問題にも当てはまりますか?
武長女子の小学1年生から高校3年生までのデータをみると、中学生年代の状況が少しみえてきます。女子の小学1年生から高校3年生までの過去1年間に「よく行った」運動・スポーツ種目(複数回答)の上位10種目を見ると、女子のサッカー経験が小学校6年生の10位にしかみられません。それも調査をしたのは2013年の6月で、2011年の女子W杯や翌2012年のロンドン・オリンピック(以下、五輪)の後です。意外に思われる方も多いと思います。W杯や五輪の影響でもっと上位にあるのではないかと。しかし、サッカーが女子に人気がないかというと、そうとも限りません。(表1参照)
【表1】女子の小学1年生から高校3年生までに過去1年間
「よく行った」運動・スポーツ種目(学年別:複数回答)
| 小学1年生(n=90) |
| 順位 |
実施種目 |
実施率(%) |
| 1 |
おにごっこ |
53.3 |
| 2 |
自転車あそび |
46.7 |
| 3 |
なわとび(長なわとびも含む) |
43.3 |
| 4 |
鉄棒 |
37.8 |
| 5 |
ぶらんこ |
33.3 |
| 6 |
水泳(スイミング) |
30.0 |
| 7 |
かくれんぼ |
28.9 |
| 8 |
かけっこ |
22.2 |
| 9 |
ドッジボール |
18.9 |
| 10 |
一輪車 |
10.0 |
| 小学6年生(n=85) |
| 順位 |
実施種目 |
実施率(%) |
| 1 |
おにごっこ |
58.8 |
| 2 |
水泳(スイミング) |
29.4 |
| ドッジボール |
29.4 |
| なわとび(長なわとびも含む) |
29.4 |
| 5 |
自転車あそび |
23.5 |
| 6 |
ぶらんこ |
22.4 |
| 7 |
バドミントン |
20.0 |
| 8 |
かくれんぼ |
16.5 |
| バスケットボール |
16.5 |
| 10 |
| 中学1年生(n=90) |
| 順位 |
実施種目 |
実施率(%) |
| 1 |
バドミントン |
26.7 |
| 2 |
おにごっこ |
25.6 |
| 3 |
水泳(スイミング) |
24.4 |
| 4 |
バレーボール |
21.1 |
| 5 |
ドッジボール |
17.8 |
| なわとび(長なわとびも含む) |
17.8 |
| バスケットボール |
17.8 |
| 8 |
ぶらんこ |
15.6 |
| 9 |
筋力トレーニング |
14.4 |
| 10 |
ソフトテニス(軟式) |
12.2 |
| 卓球 |
12.2 |
| 中学2年生(n=78) |
| 順位 |
実施種目 |
実施率(%) |
| 1 |
おにごっこ |
28.2 |
| バレーボール |
28.2 |
| 3 |
なわとび(長なわとびも含む) |
26.9 |
| 4 |
バドミントン |
23.1 |
| 5 |
バスケットボール |
21.8 |
| 6 |
ジョギング・ランニング |
20.5 |
| 7 |
水泳(スイミング) |
19.2 |
| 8 |
筋力トレーニング |
16.7 |
| ぶらんこ |
16.7 |
| 10 |
ソフトテニス(軟式) |
12.8 |
| 中学3年生(n=73) |
| 順位 |
実施種目 |
実施率(%) |
| 1 |
バレーボール |
26.0 |
| 2 |
ジョギング・ランニング |
21.9 |
| 3 |
なわとび(長なわとびも含む) |
19.2 |
| 4 |
筋力トレーニング |
17.8 |
| バスケットボール |
17.8 |
| バドミントン |
17.8 |
| 7 |
おにごっこ |
16.4 |
| 8 |
ソフトテニス(軟式) |
15.1 |
| 9 |
ぶらんこ |
13.7 |
| 10 |
キャッチボール |
12.3 |
| 高校3年生(n=61) |
| 順位 |
実施種目 |
実施率(%) |
| 1 |
ジョギング・ランニング |
29.5 |
| バレーボール |
29.5 |
| 3 |
バドミントン |
21.3 |
| 4 |
筋力トレーニング |
16.4 |
| バスケットボール |
16.4 |
| 6 |
体操(軽い体操・ラジオ体操など) |
13.1 |
| 7 |
ウォーキング |
11.5 |
| ソフトテニス(軟式) |
11.5 |
| 9 |
テニス(硬式) |
9.8 |
| ヒップホップダンス |
9.8 |
資料:笹川スポーツ財団「4~9歳のスポーツライフに関する調査」2013、「10代のスポーツライフに関する調査」2013
※「よく行った」運動・スポーツ種目:過去1年間に行った運動・スポーツのうち、実施回数の多い種目。
※サッカーは小学6年生の10位にしか登場しない。