2019.03.13
- 調査・研究
© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION
© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION
スポーツ政策研究所を組織し、Mission&Visionの達成に向けさまざまな研究調査活動を行います。客観的な分析・研究に基づく実現性のある政策提言につなげています。
自治体・スポーツ組織・企業・教育機関等と連携し、スポーツ推進計画の策定やスポーツ振興、地域課題の解決につながる取り組みを共同で実践しています。
「スポーツ・フォー・オール」の理念を共有する国際機関や日本国外の組織との連携、国際会議での研究成果の発表などを行います。また、諸外国のスポーツ政策の比較、研究、情報収集に積極的に取り組んでいます。
日本のスポーツ政策についての論考、部活動やこどもの運動実施率などのスポーツ界の諸問題に関するコラム、スポーツ史に残る貴重な証言など、様々な読み物コンテンツを作成し、スポーツの果たすべき役割を考察しています。
2019.03.13
日本で最初に作られたオリンピック公式記録映画は、市川崑監督の『東京オリンピック』であった。1965年3月に公開された2時間50分の長篇映画は大ヒットし、観客動員数は1950万人を記録する。2001年にアニメ映画『千と千尋の神隠し』に抜かれるまで、36年間観客動員数1位を維持した。昭和の映画ではナンバーワンの記録であり、2018年現在、実写映画(アニメ以外)ではいまだに1位の記録を誇っている。
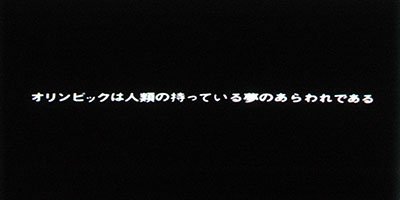
映画冒頭のメッセージ
この映画の被写体である「スポーツ」には筋書きがない。したがって、本来スポーツ映画にはシナリオなどないはずである。だが、この映画にはシナリオがあった。組織委員会が手続き上の形式的な理由でシナリオの提出を要求したようであるが、ドキュメンタリー映画のシナリオという通常あり得ないものを求められて、市川は困り果てた。そこで妻で脚本家でもある和田夏十に相談したところ、和田は百科事典で調べ、「オリンピックは大きな戦争があるときには行われていない。それがオリンピックの本質、つまり平和。映画のテーマもそれではないかなあ」と言ったという。市川はそれを「4年に1度、地球のどこか1カ所に全部の民族が集まって、楽しく運動会をやろうじゃないか、4年に1度は集まれるように地球をやっていこうじゃないか、という夢の現われなんだ。世界に大きな戦争がないことの1つの証しとして、あるいは希望として、オリンピックは行われている」(市川崑・森遊机「市川崑の映画たち」)と考えた。市川はこの映画で「平和の夢」を描こうとしたのである。

空を真っ赤に染めて太陽が昇る
さらに市川は「太陽」にこだわった。冒頭に、空を真っ赤に染める太陽が大きく映し出されるが、これは亀倉雄策のオリンピック・シンボル(現在のエンブレム)の影響が大きい。一種のオマージュであろう。
最初は要求に応じて書いたシナリオだったが、じつはそれが役立った。オリンピックでは同じ時間に複数の競技場スタジアムで競技が行われるため、全ての撮影に監督が立ち会うことは不可能である。そのため、それぞれの競技を担当するカメラマンに市川の意図を伝える役目を、シナリオが果たしたのである。
撮影にあたって市川が研究しようと思った映画、それは1936年ベルリン大会を記録したレニ・リーフェンシュタールの『オリンピア「民族の祭典」「美の祭典」』だった。本格的なオリンピック記録映画は、他になかったのである。公開されて四半世紀が経ち、その間ナチスのプロパガンダ映画という批判を受けたが、それでも『オリンピア』の評価は高かった。アーティスティックな手法を駆使した映像の美しさが評価されていたのだ。
市川はこの映画を何度も観た。すごい映画だと思った。だが、リーフェンシュタールと自分のやろうとしていることの大きな違いを発見した。
『オリンピア』は記録映画でありながら、撮り直しやフィルムの重ね合わせなど多くの撮影・編集上のテクニックを用いていた。例えば、競技が押し、夕刻になったことで明るさが不足して撮影できなくなった「棒高跳び」では、のちに別途、照明付きの"フィールド"を造り、選手に集まってもらって撮影した。西田修平と大江季雄がアップで登場する棒高跳びのシーンは、まさにその再撮影だったのである。ほかにもマラソン選手の目の位置から本人の足が撮影されているシーン、水泳選手を間近から撮ったシーンなど、競技中には絶対に撮れない映像が何カ所も見られる。そうすることによってリーフェンシュタールはスポーツをするトップアスリートの美しさや力強さを美的に表現したのである。
しかし、そうした"作り方"によって『オリンピア』は、もはや厳密な意味での記録映画ではなくなっていた。ドキュメンタリーの枠を飛び出してしまったのだ。フィクションに近い記録映画。だが、これも"映画"には違いない。
その手法を市川は学んだ。美しいものをより美しく見せ、人間をより人間らしく見せる"映画"としての完成度を高めるために、リーフェンシュタールの"作り方"を参考にした。

富士山をバックに聖火ランナーが走る
だが、実際に撮影する段階で市川は、リーフェンシュタールとの大きな違いをみせた。リーフェンシュタールが導入部から競技の記録にいたるまで、多くの場面で堂々と"作り"を行ったのに対して、市川は競技を"作る"ことはしなかったのだ。"作った"のは、競技以外の部分だけであった。例えば、聖火ランナーのシーンである。漆黒の中から聖火ランナーがトーチを持って走ってくる場面は撮り足した部分である。富士山の麓を聖火ランナーが走っていく雄大なシーンは撮り直しだ。これは実際に聖火ランナーが走ったとき、富士山に雲がかかっていて絵にならなかったため、後日、河口湖の青年団に走ってもらって撮影した。映画では、美しく純白の雪化粧をしている富士山の麓を聖火ランナーが走っている。しかし、この年の富士山の初冠雪は10月9日であるが、実際に富士山の近くを走ったのは1964年10月7日。富士山に雪はなかったはずである。
オリンピック記録映画の中心を構成する「競技」はというと、マラソンのアベベや男子100mのヘイズのような圧倒的な存在には時間をかけクローズアップするものの、必ずしもリーフェンシュタールのようにアスリートを美しく力強く描いてはいない。陸上男子100mのスタート前の選手の緊張した表情、女子100mハードルの依田郁子が持ってきた黄色いレモンのアップ、マラソンでは途中で疲れて座り込む選手、給水所で水を何杯も飲む選手などの姿を散りばめている。アベベを静かなヒーローとして描く一方、対極にいる落ちこぼれにも注目しているのだ。人間は強い者だけじゃない。勝負から脱落した者、やる気を失った者、そして彼らをながめている子どもや老人も、それぞれが"大きな運動会"の構成員として価値ある存在なのである。
市川は『映画とオリンピック 市川崑×沢木耕太郎』(「1964年の東京オリンピック」)の中で、リーフェンシュタールの『オリンピア』を「映画として、人間の肉体の美しさ、その肉体を通しての精神的な美しさまでを見事に証明している」と評価する。だが、市川が求めたのはそこではなかった。彼は「オリンピックを人間の営みとして描いた」のだった。「オリンピックというのは、競技している人だけじゃなくて、準備している人も、見物人も、みんな一緒に参加しているんだ」と言う。それこそが、「4年に1度、地球のどこか1カ所に全部の民族が集まって、楽しく運動会をやろうじゃないか」という「平和の夢」のメインテーマであった。

競技とは別に撮影したチャスラフスカの美しい演技
もしこの映画に1つだけ例外があったとすれば、それはある1人の女性アスリートの描き方であった。「競技」を"作る"ことなく撮った市川が、1人だけ競技中以外に撮影したアスリートがいたのだ。体操のベラ・チャスラフスカ(チェコスロバキア)である。スタッフが撮ったフィルムを見てあまりの美しさに感動した市川は、その美しさをさらに美しく表現したいと考えて、特別に撮影を依頼したのだ。だが、リーフェンシュタールの『オリンピア』とは異なり、「競技」を"作らない"方針を貫く市川は、そのチャスラフスカのシーンに特殊な現像処理を施した。競技中のシーンと区別するためである。
この映画『東京オリンピック』は、関係者試写会で観たオリンピック担当大臣の河野一郎が、「俺にはわからん。気に入らない」などとコメントし、それが新聞に載った。文部大臣の愛知揆一も同調し、「文部省推薦」を取り消した。この映画は「芸術か、記録か」という大論争を巻き起こした。
そのときに河野大臣と市川を仲介したのが女優の高峰秀子だった。「市川崑に頼んだらああいう映画になるのは当たり前じゃないの」という援護が功を奏して河野も矛を収め、さらに映画がカンヌ国際映画祭の国際批評家賞に輝くなど、海外から高い評価を受けたことで、論争に決着がついた。
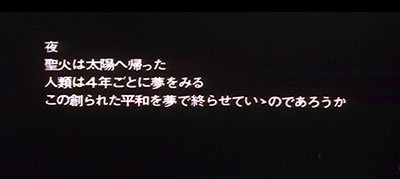
エンディングのメッセージ
そして市川は言う。
「単なる記録映画にしたくなかった。それは少しやれたような気がします。 望遠レンズを駆使して、選手の表面の逞しさだとか、美しさだけではなく、選手それぞれの内面的なものを捉えることができた」
「とにかくスポーツというのは、人間がつくった素晴らしい文化です」(JOC「市川崑総監督が語る名作『東京オリンピック』」聞き手・後藤忠弘)
市川崑の『東京オリンピック』は、そのあとに続く1968年グルノーブル冬季大会の『白い恋人たち』をはじめ幾多の美しいオリンピック記録映画に、多大なる影響を与えたのである。
 大野 益弘
日本オリンピック・アカデミー 理事。筑波大学 芸術系非常勤講師。ライター・編集者。株式会社ジャニス代表。
大野 益弘
日本オリンピック・アカデミー 理事。筑波大学 芸術系非常勤講師。ライター・編集者。株式会社ジャニス代表。