2021.03.17
- 調査・研究
© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION
© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION
Mission&Visionの達成に向けさまざまな研究調査活動を行います。客観的な分析・研究に基づく実現性のある政策提言につなげています。
自治体・スポーツ組織・企業・教育機関等と連携し、スポーツ推進計画の策定やスポーツ振興、地域課題の解決につながる取り組みを共同で実践しています。
「スポーツ・フォー・オール」の理念を共有する国際機関や日本国外の組織との連携、国際会議での研究成果の発表などを行います。また、諸外国のスポーツ政策の比較、研究、情報収集に積極的に取り組んでいます。
日本のスポーツ政策についての論考、部活動やこどもの運動実施率などのスポーツ界の諸問題に関するコラム、スポーツ史に残る貴重な証言など、様々な読み物コンテンツを作成し、スポーツの果たすべき役割を考察しています。
2021.03.17
アジアから初めて、日本柔道の父嘉納治五郎を委員に任命した1909年5月の国際オリンピック委員会(IOC)総会は、同時に1912年第5回大会の開催都市にスウェーデンのストックホルムを選んだ。国王グスタフ五世の熱意とスウェーデン政府が特設した「国営宝くじ」の収益により、ようやく万国博覧会の呪縛を解くことができた。
日本が三島弥彦と金栗四三、ふたりの選手を派遣し初めてオリンピック史に足跡を残したストックホルム大会は、その規模、運営から「理想的な」と高く評された。ピエール・ド・クーベルタンが芸術競技をプログラムに導入、公式記録映画の撮影が始まった大会でもある。

1912年ストックホルム大会に出場したジム・ソープ
問題がなかったわけではない。ひとつがロンドンで定められた「アマチュア」という参加規程に違反、陸上競技の五種競技と十種競技に優勝した米国のジム・ソープが金メダルを剥奪された“事件”である。ソープが学生時代、ノースカロライナの野球のマイナーリーグで週給25ドルをもらいプレーしていたと、大会終了半年後、米マサチューセッツの地方紙がスクープ。IOCとしても見逃せなくなった。アイルランドと米国先住民族の血を引くソープへの嫉妬と差別意識が底流にあったと言われている。
もうひとつも、やはりロンドンに端を発した「国」の問題。宗主国と属国、自治領への関わりである。オーストリア=ハンガリー帝国の属領であったボヘミアの参加(1908年ロンドンにも単独参加)にオーストリアが異を唱えれば、ロシアは自治領であるフィンランドの出場に強く反応した。
このとき、スウェーデンのIOC委員ビクトル・バルクは冷静に語っている。「IOCの認めたスポーツ領域は、政治上の領域とは異なる。オリンピックには政治上の領域に関係なく独立して参加する資格がある」――フィンランドは、外交上の配慮からロシア国旗の下にフィンランド国旗を掲げて入場行進したものの、メダル獲得数では米国、スウェーデン、英国に次ぐ第4位の好成績をあげた。
一橋大学の内海和雄名誉教授は、「この時期のオリンピックは、植民地による宗主国と属国との関連。特に後者の独立性が大きな問題であった。ここに帝国主義段階における資本主義問題の1つの大きな課題がある」と指摘する。第5回大会成功の一方で、オリンピックが政治の波をかぶる時代が目の前まできていた。
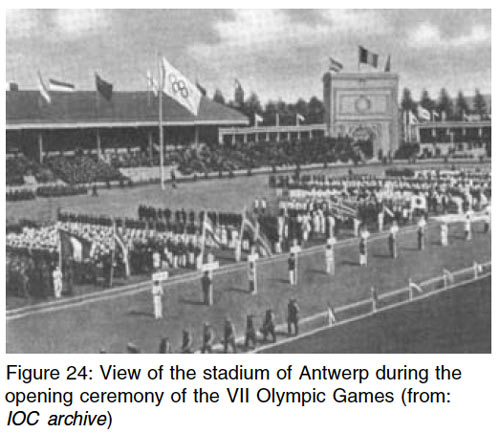
初めてオリンピック旗が掲揚された1920年アントワープ大会
欧州を舞台にした第1次世界大戦のため、1916年、ベルリンで予定された第6回大会は中止。1918年に終戦を迎えると、IOCは戦後処理を急いだ。1920年第7回アントワープ大会の開催である。この大会にはしかし第1次大戦の枢軸国側のドイツ、オーストリア=ハンガリー、ブルガリア、トルコは参加していない。IOCは参加を主張したが、開催国ベルギーが対戦国参加を望まなかった。
「アントワープ大会に選手団長として参加した嘉納は、ドイツがよばれなかったことはオリンピックの精神に反すると指摘した」――筑波大学の真田久教授に聞いた話である。
ドイツは次の1924年第8回パリ大会にも招かれなかった。1870-1871年の普仏戦争以来、フランスがドイツに抱いていた不信感の表れだったか。クーベルタン自身、ドイツを好きではなかったという。第一次大戦が起きると信頼する友人ゴートフレー・ド・ブロネーに会長代行を託し、フランス軍に従軍したのは子ども時代に経験した普仏戦争が原因だと指摘される。ただ、オリンピック運動においては、ドイツとの「連帯」に腐心した。平和運動たるオリンピックに巻き込むことで「好戦的なドイツ人の指向が抑えられると考えた」との説もある。それがベルリンでのオリンピック開催を望んだ理由だとも。
クーベルタンは翌1925年会長を退き、2度とオリンピックの舞台に顔はみせなかった。「自分の描いたオリンピックとは異なってきた」ことが要因だった。クーベルタンの悲願でもあったベルリン大会が開催されたのは1936年。しかし、ドイツの好戦的な指向は正せず、アドルフ・ヒトラー率いるナチスはギリシャのオリンピアからベルリンまで聖火を運んだリレーコースを逆に南下、第二次大戦に向けて侵略を開始したのである。
そのドイツと同盟を結び、日本が米国との開戦に踏み切ったのは1941年。第二次大戦は1940年、1944年のオリンピックを中止に追い込み、日本とドイツは1948年ロンドンで開催された戦後初のオリンピックに、開戦責任を理由に参加は許されなかった。開催国・英国の強い拒否であった。

第5代IOC会長エイベリー・ブランデージ(1964年東京大会)
「ロシア人がやってきます。どうしましょうか」――第5代IOC会長、エイベリー・ブランデージは回想録『近代オリンピックの遺産』でヘルシンキ大会の項をそう書き起こした。1917年のロシア革命を経て建国されたソビエト社会主義共和国連邦(ソ連、現ロシア)がスポーツの国際デビューを果たしたのは1946年8月の欧州陸上競技選手権である。何の前触れもなく、開催地ノルウェーのオスロにチャーター機2機で乗り込んできたソ連に、関係者はただただ慌てふためいた。
当時ソ連は国際陸上競技連盟に加盟しておらず、参加資格はない。しかし、実力行使で参加を決めると、りっぱな成績を残してしまった。やがて各競技で国際社会に加わり、1951年にはソ連オリンピック委員会を組織、IOC加盟を果たした。
オリンピックは極論すれば自由主義社会、なかでも欧州のものである。経済力を背景にした「パクス・アメリカーナ」の状況下、欧州は圧倒的なIOC委員の数で運営をリードする。IOC会長は現在のトーマス・バッハに至るまで9代を数える。ブランデージを除けばすべてが欧州出身者。その唯一の米国人会長の時代に、IOCはソ連を迎えいれた。ブランデージは言う。「鉄のカーテンが初めて上げられたのがスポーツの世界であったという事実は、国際的にみても意義が大きい」
オリンピックの政治的な利用を図る“衣の下の鎧”を知りつつ、ブランデージはオリンピックによる平和の創造という「理想」にかけた。しかし「ステートアマ」と称する国家ぐるみで養成した選手を前面に押し立てて、ソ連はスポーツの世界で影響力を増し、国際政治と同様、米国に挑む大国として「東西冷戦」に突入していった。
ソ連が資本主義国以外では初めて、1980年にオリンピックを開催した。モスクワ大会である。しかし、前年12月のソ連軍によるアフガニスタン侵攻に抗議する米国のジミー・カーター大統領が呼びかけ、カナダ、西ドイツ、そして日本など40ほどのNOCが選手たちの反対の声を抑えて参加をボイコット。閉会式で大会マスコット「ミーシャ」が涙を流す残念な大会でしかなかった。
次の1984年ロサンゼルス大会では盟主として東側陣営を率い、報復ボイコット。それが最後の輝きだったかもしれない。チェコスロバキアの「プラハの春」に始まる東欧民主化の波に抗しきれず、ミハイル・ゴルバチョフ書記長の「ペレストロイカ(再構築)」と「グラスノスチ(情報公開)」の改革を経て1991年12月、一党独裁を続けてきたソ連共産党が解体。ソ連は崩壊した。
ちなみに崩壊への引き金となったチェコの民主化運動を主導したひとりが、1964年東京、1968年メキシコシティー両大会で女子体操個人総合を連覇したベラ・チャスラフスカである。1968年大会ではソ連の弾圧により、命を懸けて国を脱出。メキシコシティーに参加した姿は「大会の華」となった。ソ連選手が観客のブーイングを浴びたのは国家の非道に対する報いとはいえ、悲しいシーンであった。
解体されたソ連の中核、ロシア共和国はロシア連邦となって再生の道を探ったものの、国際社会での影響力が薄れて久しい。「強いロシア」復活を標榜するウラジミール・プーチン大統領のもと、スポーツ強国復活をめざしたが、逆に組織ぐるみドーピングが発覚。2018年平昌冬季大会、2020東京大会とロシアとして選手団派遣ができなかった。
ソ連、ロシアに代わって米国の対抗軸となったのが中国、中華人民共和国である。
第2次世界大戦はIOC加盟国のありようを変えた。戦前、IOCに加盟していた中華民国オリンピック委員会は1949年、国共内戦の末、毛沢東が率い北京を首都とした中国共産党(中華人民共和国、以下中国)と台湾の台北に移った蒋介石の中国国民党(中華民国、以下台湾)とに分かれ、3人いたIOCのうち2人が台湾から「正統」を主張した。
IOCは1951年、彼らの主張を受け入れ、継続承認した。一方、中国の反発に1954年、台湾公認を確認したうえで、中国も承認。両者ともに1956年第16回メルボルン大会参加を認めた。両者を傷つけない配慮ではあったが、中国は選手を派遣しなかった。「台湾の旗が先に選手村に掲揚された」ことが理由だったが、本音を言えば「IOCの台湾公認」への反発である。中国は1959年までにIOCおよびすべての国際競技団体からの脱退を表明、毛沢東の文化大革命による孤立化政策を進めていった。後にIOC副会長を務めた清川正二が述べた通り、「IOCにとって中国と台湾は実に長い間の懸案」となっていく。
1971年10月、国際連合は中国加盟を承認。米国や日本は台湾残留に奔走したが、「蒋介石の代表追放」を求めた中国に抗議した台湾は国連及び国際組織からの脱退を宣言、国際舞台から去った。中国はオリンピックでも国連に準じた扱いを求めた。1976年モントリオール大会では、貿易を開始したばかりのカナダ政府に圧力をかけて台湾排除をめざした。米国の「台湾を排除するなら我々も参加しない」との意思表示もあり、政治に振り回される事態は変わらなかった。
1979年、IOCの説得にようやく2つの中国の並立が決定した。「台湾」「中華台北」ではなく「中国台北」の呼称がやがて定着していく。国連でも果たし得なかった2つの中国加盟に、IOCは「オリンピックは政治の不可能を可能にした」と自賛したが、オリンピックはNOCが加盟の単位、相変わらず政治に左右される実体は歴史が証明していよう。
中国と台湾、2つの中国問題は依然、「懸案」として続く。さらに香港やウイグル、チベット問題も含めて、IOC内部でも重きを増している中国の周辺で何が起こるのか、相変わらず予断は許されない。
南北朝鮮は休戦協定を結んでいるものの、いまだ戦争状態。とくに世界との窓口が限られる北朝鮮の動向はみえてこない。北朝鮮と韓国は過去4度、オリンピックを舞台(2000年シドニー、2004年アテネ、2006年トリノ冬季、2018年平昌冬季)に合同行進を実現させた。韓国がホストを務めた平昌では女子アイスホッケーで統一チームを急造。どれも“親北政権”での成果だが、文在寅大統領はこれをもとに2032年第35回大会の南北共同開催をもくろむ。しかし、鍵を握る北朝鮮・金正恩書記長の意向は不透明なままだ

オリンピックで使用された統一ドイツ旗
この構想を、IOCのバッハ大統領が後押しする。「オリンピック精神にかなう」との思いは当然、彼はまた1972年ミュンヘン大会フェンシングの金メダリスト。東西冷戦時代の西ドイツ代表であり、分断国家の悲哀が理解に直結していると考える。
分断時代のドイツは自由主義圏の西ドイツが先にIOCに復帰、1952年オスロ冬季大会から参加した。東ドイツは遅れて加盟申請したものの、IOCの指示で1956年コルチナ・ダンペッツオ冬季大会から「統一ドイツ」としての参加に過ぎない。1968年、ようやく東ドイツとして参加が認められたが、1989年ベルリンの壁崩壊と1990年のドイツ統一で分断は解消。東西冷戦の“あだ花”であった。
バッハ会長がどこまで実現に向けて舵を切るのか。日本人としては複雑な思いも抱きながら注目していかねばならない。政治が絡む話であり、行方は平たんではない。
最近、バッハ氏が新型コロナウイルスの感染蔓延と2020東京大会に対処するべく、「ソリダリティ」を口にする場面が少なくない。「連帯」と訳すのが、思いに近いか。コロナ禍という「新しい敵」に立ち向かうために連帯が必要であり、加盟国・地域が力を合わせて立ち向かおうと説く。
オリンピックは、5つの大陸を象徴する左から青、黄、黒、緑、赤の5色の連結した輪で表される。クーベルタンが自らデザインした「オリンピックシンボル」いわゆる五輪マークである。バッハ氏はそれを念頭に連帯を意識づけようというのか。
クーベルタンは5つの大陸すべてでオリンピックが開催されることを願った。だが、いまだアフリカ開催は実現していない。
南アフリカはかつて、人種隔離政策アパルトヘイトをとり、アフリカ諸国の憎悪の対象となった。1964年東京大会から7大会、アパルトヘイトによってオリンピックから締め出され、ネルソン・マンデラ大統領のもと1992年バルセロナ大会から戻ってきた。その南アフリカがアフリカ開催の旗頭となるのだろうか。それこそアフリカ諸国の連帯が必要となろう。政治に経済が大きく絡む。
中東での開催もない。1972年ミュンヘン大会で、「ブラック・セプテンバー」を名乗るパレスチナ武装組織が選手村イスラエル選手団を襲撃、犯人を含む15人の犠牲者を出した。オリンピック史上最も凄惨な事件である。中東の政情が、地上最大のイベントを舞台に表面化し、傷跡はいまも警備費用の高騰というかたちで残る。
はたして中東はどう動いているのか、連帯だけで解決できるほど簡単ではない。
オリンピックは政治と複雑に絡み合いながら2021年、125周年を迎えた。国連を上回る加盟206カ国・地域はほんとうに一体感をもって連帯し、今後も持続可能な存在でいられるのだろうか。クーベルタンは1929年、「もし輪廻転生というものがあり、100年後に生まれ変わったら、私はオリンピックを壊すだろう」と演説した。あと8年である。
以上は主に『オリンピックと平和』(内海和雄著/不昧堂出版) 『オリンピック全大会』(武田薫著/朝日新聞社) 『オリンピック全史』(デイビッド・ゴールドブラッド著、志村昌子・二木夢子訳原書房) 『20世紀特派員4』(産経新聞社)所収「大観衆がやってきた」(佐野慎輔)に拠った。
 佐野 慎輔
尚美学園大学 教授/産経新聞 客員論説委員
佐野 慎輔
尚美学園大学 教授/産経新聞 客員論説委員