2021.01.26
- 調査・研究
© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION
© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION
Mission&Visionの達成に向けさまざまな研究調査活動を行います。客観的な分析・研究に基づく実現性のある政策提言につなげています。
自治体・スポーツ組織・企業・教育機関等と連携し、スポーツ推進計画の策定やスポーツ振興、地域課題の解決につながる取り組みを共同で実践しています。
「スポーツ・フォー・オール」の理念を共有する国際機関や日本国外の組織との連携、国際会議での研究成果の発表などを行います。また、諸外国のスポーツ政策の比較、研究、情報収集に積極的に取り組んでいます。
日本のスポーツ政策についての論考、部活動やこどもの運動実施率などのスポーツ界の諸問題に関するコラム、スポーツ史に残る貴重な証言など、様々な読み物コンテンツを作成し、スポーツの果たすべき役割を考察しています。
2021.01.26
世界一のスポーツ王国といえばアメリカだろう。自ら体を動かす愛好者の層の厚さもさることながら、さまざまな競技の充実と、それらの競技を見て楽しむ文化が深く根づいている面などでも世界一の観がある。そこで見逃せないのが、その「見て楽しむ文化」を牽引してきた多彩なスポーツライティングだ。
新聞の報道、いろいろな雑誌の記事、さまざまな題材を掘り下げた本。アメリカのスポーツライティングの流れは、太く、力強く、豊かだ。それは王国の隆盛をがっしりと支えてきた。もし、それらがなかったら、スポーツへの関心と人気はこれほど高まらなかったに違いない。「自分でやる」「競技を見る」と同様に、「読む」もまた、王国の重要な柱になってきたのである。スポーツを励まし、讃え、時には叱咤して背中を押す最良のパートナーとも言えるだろう。
それがスポーツ界最大の祭典たるオリンピックとも手を携えてきたのは言うまでもない。スポーツライティングは、伴走者としてオリンピックの発展に力を尽くしてきた。一方、オリンピックの側も、このよき伴走者を育て、進化を促す役割を果たしてきたのである。
さて、ここでは、邦訳されている何冊かの本を通して、アメリカのスポーツライティングの豊かさを探ってみたい。そこには、スポーツを愛し、楽しみ尽くそうという思いがあふれている。それらは、スポーツ、競技、競技者の真の姿、さらにその深い魅力を知るための「窓」となっている。

デービッド・ハルバースタム「栄光と狂気」
TBSブリタニカ
最初に取り上げるのは、デービッド・ハルバースタムの「栄光と狂気」である。この本についてはこれまでにも触れているが、アメリカのスポーツライティング、とりわけオリンピックにかかわる作品群を考えるとすれば、まずこれを思い浮かべないわけにはいかない。
作品のテーマはボート競技だ。1984年のロサンゼルスオリンピックを目指してアメリカ代表の座を争う選手たちの姿が克明に綴られている。既にトップレベルの競技がビジネスと深いかかわりを持つようになっていた時代にあって、地味で目立たないボート競技は「プロとえせアマの世界にあって、(不本意ながら?)真のアマチュアリズムを守りつづけた」(本書から)状況にあった。本の原題は「THE AMATEURS」である。
著者は、そうした中で、強烈な自我を発揮しながら、苦痛に満ちた練習に耐え、アマチュアゆえの制約を乗り越えつつ、オリンピックに向けて突き進む若者たちの肖像をくっきりと描き出している。世間的にはほとんど知られることもない栄光。しかし彼らは、そのわずかな光をつかみ取るために、狂気に憑かれたかのように走り続ける。ボート競技で頂点を目指すとはそういうことだったのだ。そんな世界ならではの迫真の戦いをとことん掘り下げた作品はアメリカのみならず、世界のスポーツライティングの中でも白眉の一冊と言えるだろう。
ベトナム戦争時の米政権をテーマとした「ベスト&ブライテスト」、巨大メディアグループが舞台となった「メディアの権力」、自動車産業の勃興と衰退に焦点を当てた「覇者の驕り」――。超大国の政治や経済を牛耳る支配層の内幕を鋭くえぐり続けたハルバースタムは、スポーツをテーマとした作品もたくさん残している。バスケットボール・NBAの一チームを題材とした「勝負の分かれ目」、野球のメジャーリーグが舞台の「さらばヤンキース」などである。そうした一連のスポーツライティングでとりわけ印象的なのが、この「栄光と狂気」だ。
1934年生まれで、2007年に交通事故で急逝したハルバースタムは、まさしくノンフィクション界の巨人といえる存在である。一般に、こうして、いわゆる硬派の巨大テーマに継続して取り組む作家がスポーツに関心を寄せる例は少ない。政治や経済のような重いテーマに比べて、スポーツは「軽い」とみられがちなのだ。だが、ハルバースタムは何のこだわりもなくスポーツを題材とし、硬派のテーマと同様の徹底取材と精緻な筆致で快作を次々に生み出した。遊びや息抜きなどではなく、硬派の大作に取り組むのとまったく同じ姿勢を崩さずに、真正面から全力でスポーツを描いた。巨匠によるスポーツライティングこそ、スポーツ王国ならではの豊かな文化の象徴と言えるのではないか。
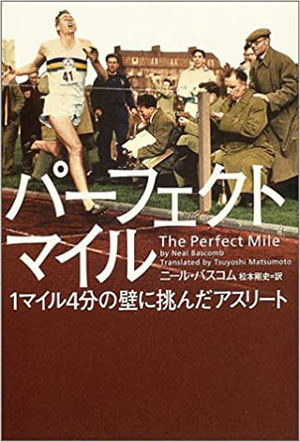
ニール・バスコム「パーフェクトマイル」
ソニーマガジンズ
次に取り上げるのは、ニール・バスコムの「パーフェクトマイル」である。1971年生まれのバスコムも、歴史的な事柄や社会問題をテーマとした作品で知られるノンフィクション作家だが、この本では、20世紀の半ばに1マイル4分の壁に挑んだ中距離ランナーを題材とした。彼もまた、取り組む価値のある分野としてスポーツを選んだというわけだ。
1950年代、欧米のスポーツ界では、陸上競技の1マイルで4分の壁を破ろうとする挑戦が大きな話題となっていた。その主役となったのは、医学を学びながら競技にも打ち込んで、ついに4分の壁を破ったイギリスのロジャー・バニスター、恵まれない育ちを乗り越えてトップランナーになり、古いアマチュアリズムの中で苦闘したアメリカのウェス・サンティ、4分突破に最も近いと目されながら「世界初」を逃したオーストラリアのジョン・ランディの3人。バスコムは、それぞれの異なった個性と挑戦の足どりを鮮烈に描き出している。
1952年のヘルシンキオリンピックを入り口に、英米豪の3人が激しいデッドヒートを繰り広げていく年月。克明な描写の裏側に、緻密で徹底的な取材があるのはハルバースタムの諸作品と変わらない。淡々とした筆から、当時の時代背景や社会の様子が生き生きと浮かび上がってくるのも同じだ。物語としての面白さと、スポーツの世界を深く掘り下げていく迫力とが読者を惹きつけて離さない力作。これも、あまたのスポーツノンフィクションの中で白眉の一冊と言えるだろう。
「栄光と狂気」「パーフェクトマイル」。アメリカのスポーツライティングの豊かさを象徴するものとしてこの二作を挙げたのは、ともに、スポーツの本質あるいは真髄に迫ろうとする姿勢が印象的だからだ。
競技の真髄は奈辺にあるのか。競技者を駆り立て、困難きわまりない挑戦に向かわせる力とは、いったい何なのか。一般のファンにはうかがい知れない深淵を目指して、二人は真正面から取材を続けていく。選手の足どりを丹念に追い、その思いを聞き取ることで、トップアスリートしか知らない世界に分け入り、そのありようをファンに伝えようとしている。それこそが、つまりは、競技の真髄に迫っていこうという姿勢こそが、スポーツライティングの真髄でもあるのではないか。
たとえば、最近の日本のスポーツものを見てみると、雑誌の記事や単行本ともに、人気競技や有名スターを取り上げた作品ばかりが目立ち、それも、単に表面の「虚像」をなぞっただけというのも少なくない。その時々に話題になっているもの、いわば「流行りもの」を題材とした企画も多いように見受けられる。極言すれば、虚像のみを追いかけて、スポーツの実像を描こうとしていないのだ。
そんな状況と比べてみると、ハルバースタムやバスコムの作品の価値はより鮮明にわかる。テーマはといえば、人気競技でも華やかなプロの世界でもない。だが、その作品は競技や競技者の実像に迫っている。スポーツライティングにはさまざまな形があっていいが、その「本道」とはやはり、こうしたものであるべきではないだろうか。人気や流行や華やかさを追いかけるだけでなく、本質や真髄や実像にしっかりと目を向けていく。そうした姿勢こそがスポーツライティングの名にふさわしいのではあるまいか。
4大プロリーグやオリンピック競技からいまだ健在のアマチュアまで、まさに百花繚乱のスポーツ王国。華やかさの一方では、地に足のついたスポーツ文化も根づいている。ここで紹介した二作にとどまらない、豊かなスポーツライティングの鉱脈は、その文化の確かさを示す証となっている。

アイラ・バーカウ「ヒーローたちのシーズン」
河出書房新社
最後には、アイラ・バーカウの「ヒーローたちのシーズン」を取り上げたい。バーカウは1940年生まれのスポーツコラムニストで、ニューヨーク・タイムズなどで健筆を振るった。この本は、それらの寄稿記事から精選して一冊にまとめたコラム集だ。
アメリカのスポーツライティングをより豊かにしてきたのは新聞や雑誌のコラムの存在である。それぞれのコラムニストが自分の個性や感性を前面に押し出して取材や執筆を行い、試合の結果を評したり競技の面白さを説いたり、問題点を鋭く論じたりするものだ。書き手の個性が売りものという新聞記事は日本には少ない。スポーツ王国ならではの魅力的なコラムは、アメリカのスポーツライティングの一方の主役ともいえる。
多くの読者を楽しませてきたコラムニストの一人がバーカウだ。その本を読むと、アメリカのスポーツコラムがどういうものかがよくわかる。
「ヒーローたちのシーズン」には合わせて45本のコラムが収められている。野球、テニス、バスケットボール、アメリカンフットボール、ボクシングといろいろな競技が舞台となっており、加えて、同じメジャーリーグの野球でも、有名選手・監督の話だけでなく、転落した元大投手、選手組合をつくった人物、統計資料の大家、ウィンターリーグでの逸話――とさまざま。一方で大学バスケットボールのスター選手の麻薬死や、ボクシングでの痛ましいリング禍が語られるかと思うと、もう一方では巨漢フットボール選手のダイエットや、野球のマイナーリーグで起きた「じゃがいも暴投事件」も出てくるという具合だ。ユーモラスなタッチもあれば、皮肉たっぷりの厳しい批判も。要するに、書き手の個性や思いをそのまま生かした幅広さ、多彩さ、自由自在な書きっぷりがアメリカのスポーツコラムの最大の魅力であり、それが多くの人気を集めているのである。
さまざまな側面を持つ幅広さ、多彩さといえば、スポーツそのものの魅力もそこに尽きるだろう。数々の競技があり、異なる技と個性を持つ選手たちがいて、種々の大会やゲームがあって、どの試合もどう転ぶかわからない。「人生いろいろ」ならぬ「スポーツいろいろ」が何よりの面白みなのだ。
オリンピックも同様。自国選手の活躍やメダル争い、人気競技の有名選手ばかりが見どころではない。世界中から選手やコーチが集まってくるオリンピックは、スポーツの幅広さのショーケースである。
スポーツいろいろ。楽しみいろいろ。アメリカのスポーツコラムはそうした魅力を凝縮したものといえる。日本にはほとんどないコラム文化がしっかりと根づいていることは、アメリカのスポーツライティングの豊かさをそのまま示している。
こうして、ここまでスポーツライティングを論じてきたのだが、締めくくりには「大いなる不安」を書かねばならない。スポーツ分野における活字文化の衰退である。
いまに始まったことではない。テレビが社会に普及し、スポーツ中継の映像があまねく届くようになって以来、新聞雑誌や本といった活字メディアの存在感は薄れてきた。テレビ映像の進化に加え、ウェブ上での情報も氾濫するようになって、その傾向はますます強まっている。
そうした中、ここで取り上げたような作品、すなわち、スポーツの真髄や本質を描こうとする「本道の」スポーツライティングはあまり見られなくなっている。先に触れたように、日本ではその傾向が顕著なのだが、王国アメリカでも状況は似たようなものではないか。華やかさや流行を追い、表面だけを矢継ぎ早に見せていくのがメディアの主流となり、緻密な取材や精緻な筆致で、じっくりとスポーツの魅力を描いていくなどという地道な手法は消えつつあるのだ。
それでいいのだろうか。スポーツを伝えるという面において、映像やSNSは万能なのだろうか。いや、そうは思えない。競技や競技者の魅力を構成しているのは、多種多様な側面でのいくつもの細かいひだであり、テレビやウェブの情報ではそうしたものは伝わりにくいように思える。さまざまな細部を積み重ねて競技の真髄に迫るのは、やはりスポーツライティングでこそ可能な仕事ではなかろうか。
スポーツにとって、スポーツライティングの「本道」はなくてはならないものだと思う。スポーツやオリンピックが最良の伴走者を失わないためにも、その灯を絶やしてはならない。
関連記事
 佐藤 次郎
スポーツジャーナリスト
佐藤 次郎
スポーツジャーナリスト