2020.11.06
- 調査・研究
© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION
© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION
Mission&Visionの達成に向けさまざまな研究調査活動を行います。客観的な分析・研究に基づく実現性のある政策提言につなげています。
自治体・スポーツ組織・企業・教育機関等と連携し、スポーツ推進計画の策定やスポーツ振興、地域課題の解決につながる取り組みを共同で実践しています。
「スポーツ・フォー・オール」の理念を共有する国際機関や日本国外の組織との連携、国際会議での研究成果の発表などを行います。また、諸外国のスポーツ政策の比較、研究、情報収集に積極的に取り組んでいます。
日本のスポーツ政策についての論考、部活動やこどもの運動実施率などのスポーツ界の諸問題に関するコラム、スポーツ史に残る貴重な証言など、様々な読み物コンテンツを作成し、スポーツの果たすべき役割を考察しています。
2020.11.06
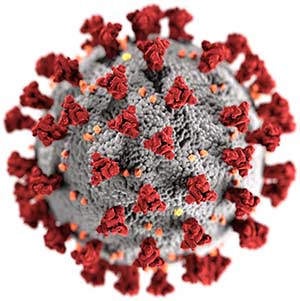
新型コロナウイルス(イメージ)
近年、オリンピックが重大な岐路に立たされてきたことは、筆者も含めて多くのオリンピックウォッチャーが指摘を続けてきたところだ。この人類最大の祭典が、深刻な諸問題を抱えるようになっていたのは誰の目にも明らかだったのではないか。
しかも、そこに思いもよらない新たな苦難が突如として降りかかった。コロナ禍である。これにより、オリンピックはかつてない苦境に直面することとなった。すべてを一から見直さなければならないかもしれない。それほどの窮状に、現在のオリンピックは置かれている。
まず、コロナ禍が降りかかる以前のことを振り返っておこう。果てしない拡大路線が生んだゆがみが諸処に出ていたのをまず挙げねばならない。一応、参加者の上限数が設定されているとはいえ、夏季には一万人以上の選手が集まり、三百をはるかに超える種目が実施されるほどに肥大化した大会は、それに伴って、豪華さ、きらびやかさを競う競争もエスカレートさせ、時には国家の(政権の?)威信を示すための機会にも利用されて、かつてとは比較にならないほどの巨額資金を必要とするようになった。そのことが招き寄せてしまったのが、主要都市のオリンピック離れである。
近年、オリンピック開催招致に関しては、当初、立候補=開催に意欲を示していた欧米の都市が、あっさりと招致活動から撤退していくようになっている。最初は冬季大会からその傾向が始まったが、すぐ夏季の招致にも波及した。あまりに膨れ上がった開催経費の負担には耐えられないし、そのような招致活動には一般市民の賛同は到底得られない――と各都市が判断せざるを得なかったからだ。結果、夏季でも冬季でも立候補が激減し、東京やパリ、北京、ロサンゼルスといった、一国にも相当する財政基盤を持ったスーパー大都市に開催が偏る傾向が強まりつつある。かくして、以前なら十分にホストシティーになり得た主要都市のオリンピック離れが加速し、世界のさまざまな地域、多様な文化のもとで順次開いていくはずのオリンピックの基本理念が消えかけているのである。
こうした状況がもたらされたのは、国際オリンピック委員会(IOC)をはじめとする関係団体がビジネス重視の路線をとり続けてきたからでもあるだろう。1970年代に壊滅的な財政破綻によって消滅の淵にも立たされたオリンピックは、その後、民間資金の導入によってよみがえり、空前の繁栄を謳歌するまでになったが、それはまた、すべての面でビジネス最優先、収益拡大の方向性を極限まで強めるようにもなった。その結果として、本来は主役であるべきスポーツやアスリートが、ビッグイベントのコンテンツのひとつにすぎない状況に追いやられているようにも見える。この面でもまた、オリンピックの大切な理念がないがしろにされていると言わねばならない。
そこでどうなったか。世界一オリンピック好きな国民といわれる日本でも、近ごろは、オリンピックに対する市民の声が集められるたびに、「金儲け主義になっているのではないか」「アスリート・ファーストになっていない」などの批判がひんぱんに聞かれるようになった。「世界一好き」でもそうなのだから、これはどこの国でも同じ傾向にあるに違いない。つまり、オリンピックの繁栄を支えている草の根のファンたちの間でも、オリンピック離れが広く進んでいるということだ。
これらが、近年のオリンピックを取り巻く状況のありのままである。繁栄のただ中にいるように見えても、さまざまな面でオリンピック離れが進んでいる。このままの状態が続けば、至高の存在どころか、衰退の二文字が現実のものとして見えてくるだろう。新時代に向けて、具体的な変革に踏み切らねばならない時期が来ている。そうしなければ、多くの人々に見放されてしまいかねない。オリンピックが重大な岐路に立っているというゆえんだ。

オリンピックシンボルのモニュメント(背景は国立競技場)
というわけで、とりあえずは、オリンピックが直面するようになった危機的状況について書いてきたのだが、これらは何度でも繰り返し論ずべき問題であるとはいえ、既に再三にわたって指摘されていることだ。それでもなお、あえてここまで書き連ねてきたのは、先に触れたように、そうした状況に加えて、さらに突如として、オリンピックの存続を根底から揺るがしかねない巨大な危機が降りかかってきたということを強調したいからだ。危機の二乗によって、かつてない窮地にオリンピックが追い込まれたことを指摘しなければならないからだ。全世界を覆ったコロナ禍は、オリンピックにとって、それほどに重大な問題である。
またたく間に世界各地に広がった新型コロナウイルスの蔓延は、人々の日々の暮らしを根底から変えてしまった。その荒波は暮らしのすべてに及んだ。当然ながらスポーツも例外ではない。ことに大きな影響を受けることになるのがオリンピックなのだ。
グローバリズムの波に乗って、あっという間に世界中に拡散したコロナ禍。国内でも感染が広がり、一時は非常事態宣言も出された。それはとりあえず解除されたが、収まりつつあるように見えたのはつかの間で、すぐに第一波を感染者数でははるかに上回る第二波がやってきた。「withコロナ」の言葉も語られてはいるが、その後、感染者数がある程度落ち着いてきたとはいえ、先行きが見えない状況はまったく変わっていない。感染者数が減っていったとしても、ワクチンが開発されたとしても、社会全体が、感染拡大の不安にさいなまれながら、半ば手探り状態で進んでいかねばならない日々は、まだ当分続くのではないだろうか。
コロナ禍は、人と人との触れ合いをできる限り避けねばならないという制約を現代社会に課した。近現代の歴史において、人々がほとんど初めて直面する難題である。となれば、グローバリズムのひとつの象徴ともいうべきオリンピック、200以上の国・地域から選手と関係者、さらには観客たちが一都市に集まる世界最大の祭典が、コロナ禍のただ中ではらむリスクははかり知れない。同時に、そのはかり知れないリスクを抱えた巨大イベントに対する人々の視線が、きわめて厳しく、冷ややかなものになるのもまた、言うまでもない。すなわち、コロナ禍のもとでは、オリンピックがいままでとはまったく違った立場に置かれるということだ。
2020年東京大会は2021年に延期された。これだけでも異例中の異例だが、欧米や南米で感染拡大がなかなかおさまらず、他の地域でも今後の蔓延が懸念される状態では、2021年の開催さえも危ぶまれている。IOC側は「(コロナ禍による)制限下でも大会を安全に開催できる」と強調しているが、「こうすれば開催できる」という具体的な道筋を示しているわけではない。「絶対ありえない」といわれた史上初の大会延期を選択の余地なしで受け入れざるを得なかったことだけでも、オリンピックにとってコロナ禍がいかに大きな脅威かが否応なしにわかる。
また、この状況が、既に過剰な規模拡大や経費増大によって激減している開催希望都市を、立候補からさらに遠ざけるのも避けられないだろう。コロナウイルス感染の不安がなかなか消えないとすれば、自国での感染拡大をわざわざ招き寄せるような真似はどの国もするわけがない。そうして、開催の引き受け手に窮するようになれば、その先には「オリンピック消滅」の可能性さえちらつくことになる。数々のトラブルを経験し、乗り越えてきたオリンピックだが、この危機ばかりはかつてなかったほどの難局と言わねばならない。
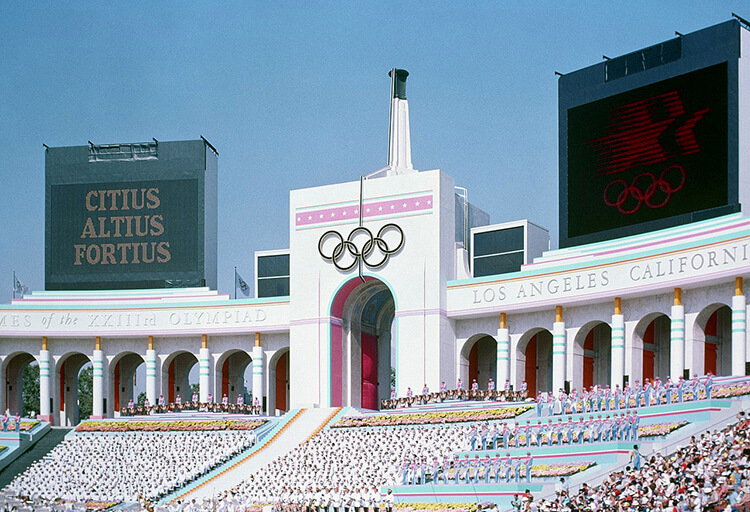
1932年大会、1984年大会でも使用されたロサンゼルスメモリアルコロシアムは、2028年大会でも使用される予定(写真は1984年の開会式)
では、その困難な状況に対して、オリンピックに関係する者たちは、いま、何をすべきなのか。
ひとつは、オリンピックのあり方をあらためて省みることだろう。とめどない規模・経費の膨張と、これもとどまるところを知らない豪華さと華やかさの競争。オリンピックはもはや、スポーツの祭典としての本質を打ち捨て、巨大ビジネスの舞台として、すべての面で商業的な成功が優先されるイベントとなっている。そのゆがみに嫌悪感を持つスポーツ人やファンは少なくないが、経済面における繁栄がそこから関係者の目をそむけさせてきた。が、先に述べたように、その際限のないエスカレートが限界に近づいているのは明らかだ。
社会のあり方や仕組みそのものを大きく変えてしまったコロナ禍。ただ、だとすれば、これは種々の変革の機会ともなるはずだ。未曾有の危機は、オリンピックのあり方を根本から見直す好機でもあるのではないか。いまこそ、すべてのスポーツ人、オリンピック関係者は、オリンピックのゆがみに正面から向き合い、あるべき新たな将来像を打ち立てるべきではないだろうか。
東京大会に関しては、さまざまな面での簡素化が必要だとして検討が行われ、IOCと大会組織委員会によって52項目に及ぶ簡素化策が策定された。コロナ禍に「強いられた」対策とはいえ、あるべき見直しのひとつには違いない。が、大会関係者数の削減(10〜15%)や競技会場などの装飾削減以外は細かな点ばかりで、思い切って踏み込んだ策とは到底言えない。
さらに難しい課題は、その東京大会を、いったいどのような形で開くかということだ。2021年になんとか開催に漕ぎつけたとしても、その時点で世界のコロナウイルス感染が終息に至っている可能性は低い。ワクチンや特効薬がまんべんなく普及しているかどうかも不透明だ。そうした中で大会を開くには、いったいどうすればいいのだろうか。
発表された52項目の簡素化案は、感染防止のためにはあまり役に立たない。では、どのような選択肢があるのか。まず考えられるのは無観客開催だろう。大幅な種目減や分散開催もひとつの方法だ。いずれも、これまでの「オリンピックの常識」なら絶対に受け入れられない措置だが、現状はそんなことにとらわれてはいられないところまで来ている。「すべて一から」というゆえんである。
といって、そうした策を講じれば開催できるのかと問われれば、首を横に振るしかない。誰もがすぐに思いつくようなことだけでは、とても十分とはいえないだろう。コロナウイルスの不安が残る中で、開催国・都市、各国選手、関係者、そして世界中のスポーツファンの多くが納得して開催を受け入れる大会にするには、いったいどんなアイディアがあるのだろうか。この超難問にある程度の答えを出さない限り、祝福され、歓迎されるオリンピックにはなり得ない。
しかし、いまのところ、この未曾有の危機に際して、これらのことをこぞって論議する声は聞こえてきていない。もちろん、IOCや大会組織委員会はさまざまな状況に応じた対応策を慎重に検討してはいるだろう。ただ、オリンピックが人類共通の貴重な財産である以上、上記のような根源的な問題についてはできる限り幅広く、公開の場で公明正大に論議が行われ、それに基づいて最終的な結論が出されるべきではないか。その点からして、いつになっても広範な論議がわき起こってこないのには大いに疑問を感じる。
現在のオリンピックは、スポンサーやテレビ局を筆頭とした数多いライツホルダーによってがんじがらめになっている。IOCや日本オリンピック委員会(JOC)など各NOC、また各競技団体や大会組織委員会もそうしたしがらみに縛られており、根本的な改革やいままでにない形での開催について声を上げるのには消極的だ。であるなら、そんなしがらみにとらわれていないスポーツ関連団体やメディア、研究者や一般のファンなどがまず声を上げ、論議の口火を切るしかないように思う。そして、これからのオリンピックはどうあるべきか、いままでとはまったく違った形での開催が可能かどうか――について幅広い論議を巻き起こしたい。それはもう、待ったなしで進める必要がある。
過剰なビジネス優先の姿勢が生んだ数々のゆがみ、そこから生まれたオリンピック離れにどう対応するか。全世界を覆ったウイルス蔓延をどう乗り越えるのか。危機の二乗は、近代オリンピックが直面する最大の難問である。IOCなど直接の当事者だけに任せておくわけにはいかない。答えを出すには、できる限り多くの知恵、アイディア、発想が必要となる。オリンピックに関心のある世界中の人々こぞっての論議の形をぜひとも構築したい。オリンピックをどんな形で存続させるか。あえて言えば、どう生き残らせるか。それを考え、実行に移すために与えられている時間は、けっして長くはない。
 佐藤 次郎
スポーツジャーナリスト
佐藤 次郎
スポーツジャーナリスト